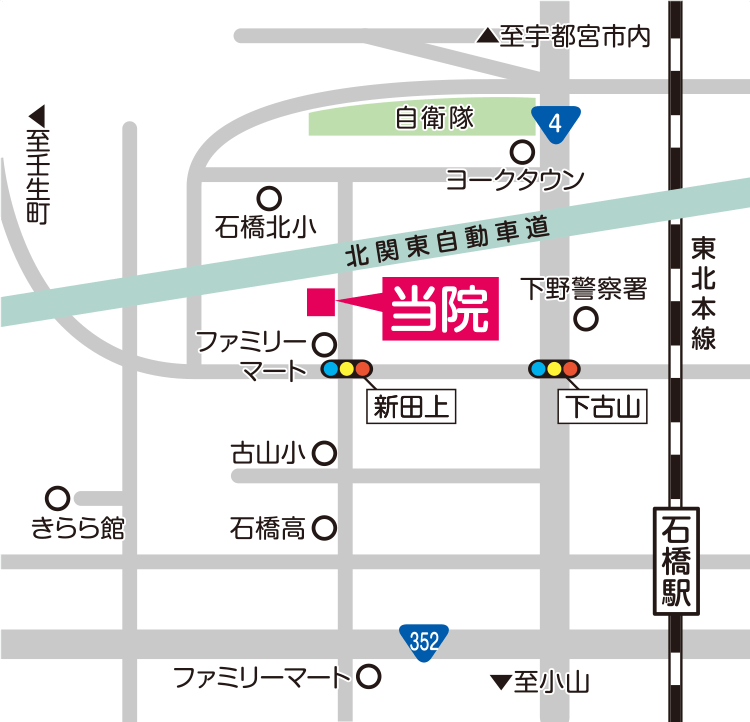発達性協調運動障害とは

大きな病気やケガ、筋肉や神経などの明らかな異常がないにも関わらず、乳児期からの運動発達の遅れ、幼児期の日常生活の困難さ、運動の苦手さがみられ、いわゆる不器用さが極めて大きい障害のことです。
学童期以降、学習障害の併存や不登校、引きこもりなどの二次的な心理・社会的問題に発展することがあります。
「協調運動」とは、身体のいくつかの部分をつなげた運動のことです。協調運動には、①手先を使うもの ②体全体を使うもの ③目と手の動きを合わせるものがあります。これらの苦手さがあると、生活や学習での「困り感」が増えてしまいます。
運動を楽しみ、運動習慣を身につけ、心と身体に健康な生活を続けていくことは、大人になっても大切なことです。日常生活の困難さを、「不器用」「本人の努力不足」などの言葉で片付けることはできません。
協調運動障害に早期から目を向け、本人が安心して日常生活を送れるよう本人、本人を取り巻く環境を考えていくことが大切です。
特徴
| 乳児期 | 幼児期 | 学童期 |
|---|---|---|
|
|
|
主な治療法
それぞれの子どもの発達段階をベースに、どこでつまずいているのか、何に苦手さを感じているのか感覚・運動面、姿勢やバランスなどの評価をします。
本人が「やってみたい」「チャレンジしたい」と思えるように、課題の工夫、環境の工夫、家族を巻き込んだ工夫をしていきます。気長な気持ちで、苦手なことや新しいことに少しでもチャレンジし、達成感を得られるよう、総合的に支援していきます。